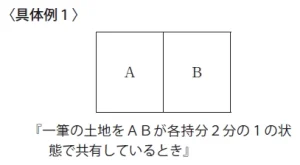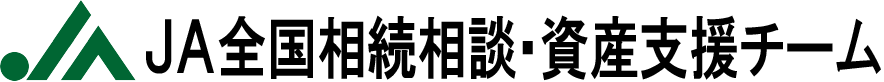JA 全国相続相談・資産支援チーム 顧問 弁護士 草薙 一郎
はじめに
今回は、相続回復請求権と不動産の時効取得との関係について、令和6年3月19 日に最高裁判所の判決が出されているので、このことについて説明したい。
相続回復請求権とは
民法884 条
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20 年を経過したときも、同様である。」
この条文の意味について最高裁判所は、昭和53 年12 月20 日の判決で以下のように述べている。
①相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定して、相続の目的である権利を侵害しているときに、真正相続人が表見相続人に対して自分の権利を主張して、その侵害を排除して、真正相続人の相続権を回復させようとするものである。
② 884 条が権利を主張の期間を設けたのは、表見相続人が外見上相続したのかのような事実状態が相当期間経過することで、この状態を覆滅させる真正相続人の権利を回復することは、かえって第三者の権利義務に混乱が生じることからである。
この相続回復請求権が生じるケースであるが、共同相続人のひとりが、勝手に単独登記をしているような場合、共同相続人の有する法定相続分を、他の共同相続人が侵害していることから、このようなケースでは、この相続回復請求の問題となる。こういうような場合には、単独登記の抹消登記を求めることになる。
ただ、このケースで相続回復請求権が問題となるとすると、民法884 条の権利行使可能期間が経過してしまったあとでは、単独登記をした相続人は、他の真正相続人からの請求に対して5年又は20 年の経過があると主張できてしまうことになる。
これでは、自ら違法な処理をしている者を助ける結果になることから、裁判所は、こういうケースでは単独登記をした表見相続人は相続回復請求権の消滅時効の主張はできないとしている。
取得時効との関係
では、共同相続人が自分しか相続人はいないとして単独登記をしていた場合も同様と考えていいのだろうか。この件については、下級審や学説ではいろいろな結論がだされていた。
今回前述した最高裁判所の事案は、簡単に言うと以下のような内容である。
相続人は養子のXがひとりであるが、被相続人は生前遺言書を作成して、親族に不動産を分与する旨の遺言を作成し、その遺言書は他の文書とともに分与対象者に交付していた。被相続人が死亡し、戸籍上は唯一の相続人であるXが対象不動産を相続したと信じ、X単独名義の登記を設定した。
ところが、事実認定の問題は裁判所の中でいろいろあったようであるが、相続開始から17 年を経過したときに、遺言執行者が選任され、おそらく、対象不動産は被相続人から遺言で遺贈されていると当該親族が主張した。これに対してXは、他の親族への法定相続分(共有持分)に対して、取得時効を援用した案件である(なお、遺言は包括遺贈の内容である。)。
この事案の前提として、①Xは戸籍上唯一の相続人であり、遺言の存在を全く知っていない。そのため、Xの主張する時効については、自分は占有開始にあたり善意、無過失であるとの前提の時効期間10 年間の時効の援用であること。
②遺言で相続した(包括遺贈)と主張する真正相続人については、遺言書の存在は知っていたと原審では認定されていること。あわせて、③この事案は今回の民法改正前の事案であり、遺言について第三者の登記前に登記しないと、遺言の内容を第三者に対抗できないということにはならず、遺言の効力が登記に優先していた時代のものであることである。
このうち、②については、仮に相続回復請求権が5年で消滅としても、前述のように、表見相続人にこの時効の援用を認めていいかの議論は残っている。
以上を前提に、この事案を説明したい。
Xは唯一の相続人であることから、遺言を知らずに登記をつけ、対象不動産を10 年間継続して占有をすれば、時効取得の要件を充足する。
反面、遺言で取得できるとされた者は、対象不動産を取得できるはずの者であり、もし、遺言内容を知っていなければ、相続開始から20 年以内であれば、Xに対する相続回復の主張は可能なはずである。そうすると、相続回復請求権の時効期間前に、対象不動産について取得時効の要件を充足した者は、遺言で取得する者に取得時効を主張できるかが議論されることとなる。
これについて、前述の最高裁判所は、民法884の相続回復請求権と民法162 条の所有権の取得時効とは要件、効果を異にする別個の制度で、特別法と一般法という関係にはない。また、民法その他の法令では、相続回復請求権の相手である表見相続人が、その消滅時効完成前に、相続回復請求権を有する真正相続人の相続した財産の所有権を時効で取得することを妨げる旨の規定はないとしている。さらに、相続回復請求権の消滅時効は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させるものであるところ、表見相続人が取得時効の要件を充足しているにもかかわらず、相続回復請求権の消滅時効が完成していないことで、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することを妨げられるとすることは、前記趣旨に整合しないとし、「以上によれば、上記表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。」として、本件Xの登記を抹消する必要はないとした(判例時報2612 号31 ページ以下参照)。
コメント
本件は相続回復請求権という少し聞きなれない制度であるが、何らかの参考になればと考える。