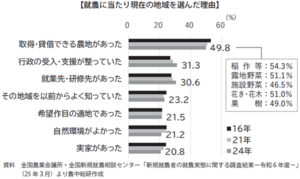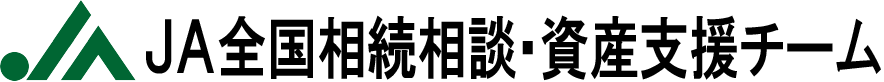JA 全国相続相談・資産支援チーム アドバイザー(JA 世田谷目黒 元相談役) 床爪 晋
早いもので、農協改革集中推進期間が2014 年6月~ 2019 年5月迄、改正農協法成立2015 年4月、2016 年4月施行と10 年が経過し、2019 年4月には公認会計士監査が導入され、同年9月には中央会が組織変更により一般社団化し、全中の指導権がなくなる等農協叩きが実施されました。
原因は色々あると思いますが、一つとしてTPP 反対から始まる官邸主導を読み切れず、今迄通りの族議員頼みの失敗にあると思います。しかし、現場ではもっと深刻な事態になってきたのが、経費削減に伴う職員の削減。特に、組合員と
の接点の縮小です。要するに失われた30 年の途中にコロナ禍が重なり、何れの金融機関も職員数の縮小を行っていました。農協も渉外職員の減少に努め、収支の向上のみを目指し、他の機関を見習って行った結果、組合員との接触が少なくなり、全ての事業に於いて情報の収集が出来なくなり、結果、組合員の声が聞こえなくなって、組合の存在価値が減少してしまいました(コメの集荷減少も此処に在るかな)。
また、今回農林中央金庫が外国債券運用の失敗で2025 年3月期は1.5 兆を超える最終赤字を出しましたが、再び資本増強の依頼を行い、格付け会社の格付け引き下げを防止でき、資金の調達も無事行う事が出来る見込みでありますが、以前の二回(住専、リーマン)の時は指導機関が全国中央会でありました。今回は、全中に指導権がないなかで、単協への影響は避けられないのでは無いでしょうか。外部識者より運用体制の見直しが急務である。と同時に、理事会に運用の責任者が少ない事を問題視され、外部の専門人材の登用を進められているとの事であります。そもそも、農中には優秀な人材が多く在籍をしていたと思います。例えば、国の年金の運用会社年金積立金管理運用独立行政法人の理事長は、この3月までは、金庫の元副理事長であった宮園雅敬 氏でした。前任の理事長は金庫の元専務 高橋則広 氏両氏とも、相当の収益を上げておられます。その他、その筋で多くの方が活躍されています。決して専門家が居ない訳ではないと思うのですが。
そもそも我らが組織は、昔から上の指示がそのまま下に流れる構造になっており、素晴らしい面もあるが、一方なかなか流れに逆らう事は難しい雰囲気であります。全国連の考え方がずれていても途中修正が出来ず、下まで流れてしまう悪い面があります。皆さんも覚えていると思いますが貯金100 兆円を集める運動。運用先もなく、ほとんどの金融機関は資金の獲得に消極的に対応していたが、JA グループは集めてしまいました。結果はご存じの通り運用できず、挙句は集めるな。一定残高以上には、奨励金は出さない。無駄な集金はするな。低金利政策が続いていれば良いかもしれないが日銀の総裁が代わり、少しずつ金利のある世界に移行してくる時代に入っています。単協が、一度行ったことを元に戻すことは大変です。組合員一言、農協さんはお金いらないよね、集金に来てくれないから。この時、大手銀行では、金融業務の柱を顧客の相談相手となって、資産情報収集と、その運用業務により収益を出すことに方向転換していました。そして、やっと全国連は相続相談を強化しようと、相談業務として組合員の悩みの声に耳を傾けよう。と舵をきってくれました。ここまで来るのに、平成9年(1997)の第21 回JA 全国大会より27 年間が掛かりました。
農協を取り巻く環境は、人口減に伴う中長期の事業環境の悪化、マイナス金利下で縮小した事業の復活、日銀が利上げを進める中どう対応するのか、じり貧で縮みゆく道を選ぶのか、攻めに出るのか。攻めに出るなら中金、各連合会はどのような支援を行ってくれるのか、早急に結論を出さなくてはならないと思います。ここは苦しいと思いますが、十分に肥料を与えて地盤強化しなければ、すべてが消滅をしてしまうのではないでしょうか。
組織全体としてラストチャンスと捉えて、その上で各単協が有る程度(単協は決して一人では生き残れない、協同組合の理念である小さな力を集めて大きな力と知恵の塊になる、それが連合会の役割と思う)の独り立ちが出来る様に準備をさせるべきと思います。
今からでも遅くはない独り立ちの準備
それでは単協が何をすればよいのか…また、出来るのか… 基本はもう一度原点に返り、目線を組合員に向けることが第一です。
ご存知の通り組合員は顧客ではない利用者でありオーナーです。単協の常勤役員と職員は、オーナーから執行を任されているだけです。オーナーは自分にとって利用価値が無くなれば離れていくのが当然でしょう。利用価値を聞き出すためには、会話が必要となります。価値とは、単に金銭のみでは無い事をご存じと思う当事者が困った時や考え方が纏まらないときに、相談相手になってくれることが一番で、その対応が組合員目線で出来るかどうかで価値が生まれます。
その価値こそが農協の存在意義(パーパス)であるので、このパーパスをもう一度再確認する必要がある。
そして、そのパーパスを達成する為にいろいろな事業方針を作ります。その方針も基礎となるモラルが有ってこそ成り立ちますので、注意が必要です。方針達成のために禁じ手を使うようなことは勿論駄目で、ここは法令順守をしっかり入れて下さい、おのずと組合員目線も出来ていると思います、組合の利益は二番目です。
それでは、組合員全員に共通する農協の存在意義は何か?
それは困った時の相談相手です。何かあったら聞きに行くところが無いと困る。だから農協が必要であるとの声が有れば、この事が存在意義となります。
その困り事は何か、組合員の全てに通じる事は相続問題です。組合員の皆さんは、土地・家屋の不動産をお持ちです。特に、農地、山林、宅地、事業の土地等いろいろ持っておられます。困ったことに令和6年4月より、必ず相続した不動産の名義変更登記をやらなければならない事になりました。その土地・家屋の価値が有ろうが無かろうが、行うのです。
一口に登記すればとおっしゃいますが、登記まで手続きを進める事が非常に大変です。まず、第一に相続を争族にしないことが肝心です。
私の経験では、こんな事で相続時に揉めて、困ってしまいました。
| ・遺言書が無い場合 ➡ | 分割に関するトラブル、名義変更や解約が出来ない、連絡が取れない相続人が居た、相続人の数が多かった、相続人の配偶者が要求してくる、他色々 |
| ・遺言書が有る場合 ➡ | 遺留分侵害請求 |
『万が一相続税が掛かる場合、相続が発生したら10 か月はあっと言う間』
だから事前の準備対策が必要 ➡ 農協の存在意義
組合員の第一の要望は節税対策と思っていませんか?(誰しも刷り込まれています)
税金対策は二番目以降、一番の対策は争いごとを避ける事(結果節税になる)
争いごとを避けるには
公正証書遺言の作成支援と、遺言書の重要性と価値
〇書きたくなるポイントとアドバイス
- 被相続人の意思が相続人に直接伝えられ、法定相続を回避することができ、事業の承継が可能
- 子供たちの争いを見たくない配偶者への配慮
- 相続登記の名義変更や金融資産の名義変更、払い戻しがスムースになる
- 税制の特別控除が受けられ易く、節税になる
- 相続税の計算や、納税の準備ができる
- 一番重要なのは、最近特に増大している老・老相続の弊害防止になる
〇付言事項の追加
必ず、なぜこのような遺言を書いたのか、自分の思いを入れる事で争いを少なく出来る。
例:
私は大和家を守り繫栄させたいと思い、大和家の主要な財産と、祖先の祭祀を長男〇〇に相続させることにしました。私は自分の人生を振り返り、家を守る事がいかに難しいかということを痛感しております。
今の平穏な人生を送れた事は、妻が私のよき理解者であったと同時に、素晴らしき子供たちを育て上げてくれた結果と、感謝いたします。〇〇は、私から相続した財産は自分個人の財産ではなく、代々引き継いでいく大和
家の財産であることを自覚してください。
家族の争いが起きる事は大和家を守っていくうえで最大の障害となりますので、〇〇は大和家の親戚一同兄弟姉妹の事にも気を配り皆が本家にいつまでも顔を出せるような良好な関係を維持して下さい、この遺言書が守ら
れることを強く願います。
以上
遺言書は、自筆遺言書でも公正証書遺言でも、いずれでも良いですが、出来れば専門家の立会いの下の公正証書の方が説得感有ります。その場合、立会人が必要となりますが、積極的に農協が関与して勤めて上げれば満点です。
ただ、一つ注意しなければならない事は、これは個人の秘密事項でありますので、守秘義務は徹底的に実行してください。組合員との信頼関係の基礎となります。昨年、ある県の女性部の相談業務の研修会でお話ししたところ、ご出席の役員の方が、農協で遺言書の相談を聞いてもらったら、村中に私の財産内容が知れてしまうので怖ろしくてできない。だから、信託銀行で作成したと話していらっしゃいました。誤解を解くためにも、積極的にこの問題を取り組んで頂きたい。
相談業務は経営の柱、各事業連携の中心であり経営基盤の基です。
これが出来るのは農協で有り、総合事業の強みであります。
相談業務は種々雑多
営農関係、税務関係、法律関係、登記分筆関係、測量関係、遺言関係、その他
何れも各関係機関と専門家との連携を密にし、解決にあたる事。しかし、決して専門家への丸投げは自分と組合員の為にならないのでやらないこと。
JA グループの皆さんが、組合員の声に耳を傾けて、相談業務に取り組んでくださることを、願っています。
以上となります。